団体賛同3,486団体、個人署名33,163筆を文部科学省に提出しました!

すべての人が学べる社会へ 高等教育費負担軽減プロジェクトは2月18日、「私とあなたができること 高等教育費の負担軽減を求めよう」の取り組みである団体賛同3,486団体(最終集約2025年1月31日)、個人署名33,163筆(第二次集約2025年2月17日)を取りまとめて文部科学省へ提出、要請を行いました。
冒頭、大内裕和さん(武蔵大学教授)、室橋祐貴さん(一般社団法人日本若者協議会代表理事)、南部美智代さん(労働者福祉中央協議会事務局長)が、文部科学省高等教育局学生支援課の桐生崇課長へ署名簿と要請書を手交しました。

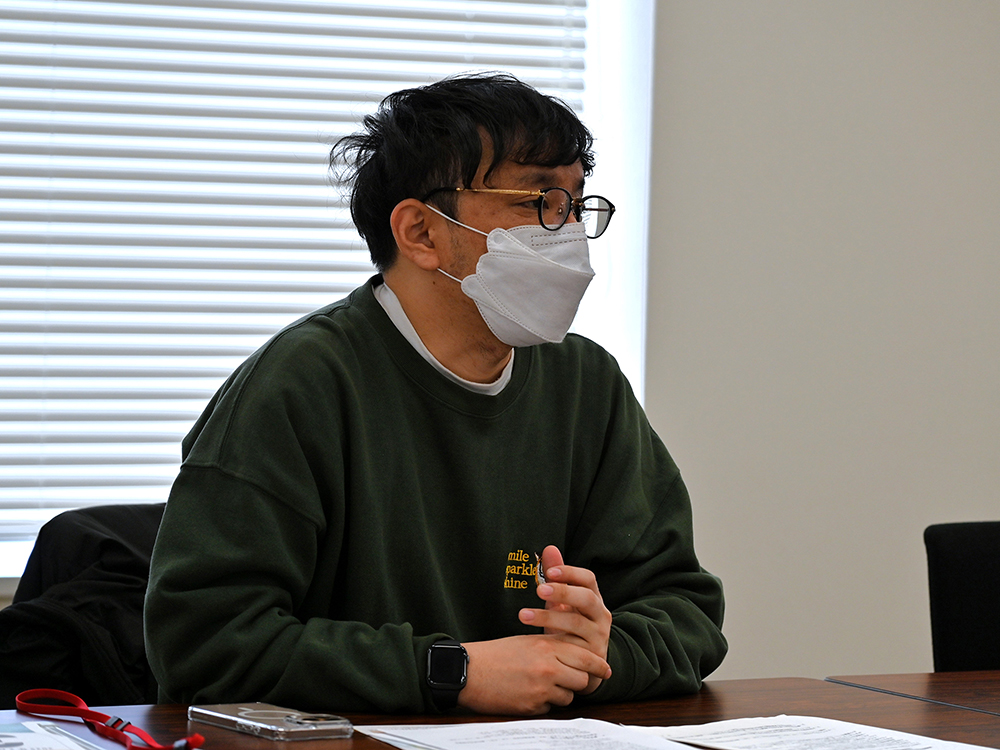

続いて大内さんが3点の要望事項について根拠を示しながら説明しました。特に出生数が政府予想を大きく上回って減少していることにふれ、「社会構造全体の破綻を防ぐためにも何らかの手を打たなければならない。中間層への教育費負担軽減を行う必要性が増大している」と述べました。
桐生課長は限られた財源の中で工夫して進めているとし、「多子世帯は家計に占める教育費負担が大きく、同時に扶養している場合はさらに負担が大きくなるため、まずはそこに支援のターゲットを絞って今回の条件設定となった」と説明、支援対象のさらなる拡大には恒久財源が必要とのことで、「今後、財源をみながらさらなる施策を検討していく」と答えました。
その後の意見交換では、室橋さんが「いま、中間層が苦しい状況。さまざまな制度も年収制限があり、不満が高まっている。社会的な分断を危惧している。よりユニバーサルな制度を構築し、少額でもまずはすべての人が支援を受けられるようにしていくことが社会的な合意につながっていく」と指摘しました。

南部さんは「当事者の声に耳を傾けてみても中間層からの不満の声が多い。自身がダブルワークやトリプルワークで生活し、懸命に子どもを育てているのに、年収を条件にさまざまな支援の対象から外れている。今回は一歩前進と受け止めているものの、やはり社会的な分断が危惧される。働き方から学び方まで全体的に捉えていかなければならない」と寄せられた声を紹介しました。
最後に大内さんは「普遍主義的な制度に向けて高等教育予算を増やすよう今後も強く要請する。ぜひ前進させていただきたい」と強調し、意見交換を終えました。文部科学省への要請は2024年11月13日の中間集約に続き2回目でした。
わたしたちの取り組みでは「団体賛同」は2025年1月31日で最終集約としましたが、change.orgでの「個人署名」は当面の間、取り組み期間を延長することとしました。おひとりおひとりのご署名が制度を変える力になります。ぜひ引き続きのご協力をお願いします。
また、わたしたちは2月13日に「高等教育費の負担軽減を求める院内集会」を開催しました。当日の模様はYouTubeで視聴できます。下記URLよりぜひご視聴ください。
同院内集会の模様は当ウェブサイトの新着情報にも掲載しています。こちらの記事もあわせてご覧ください。
