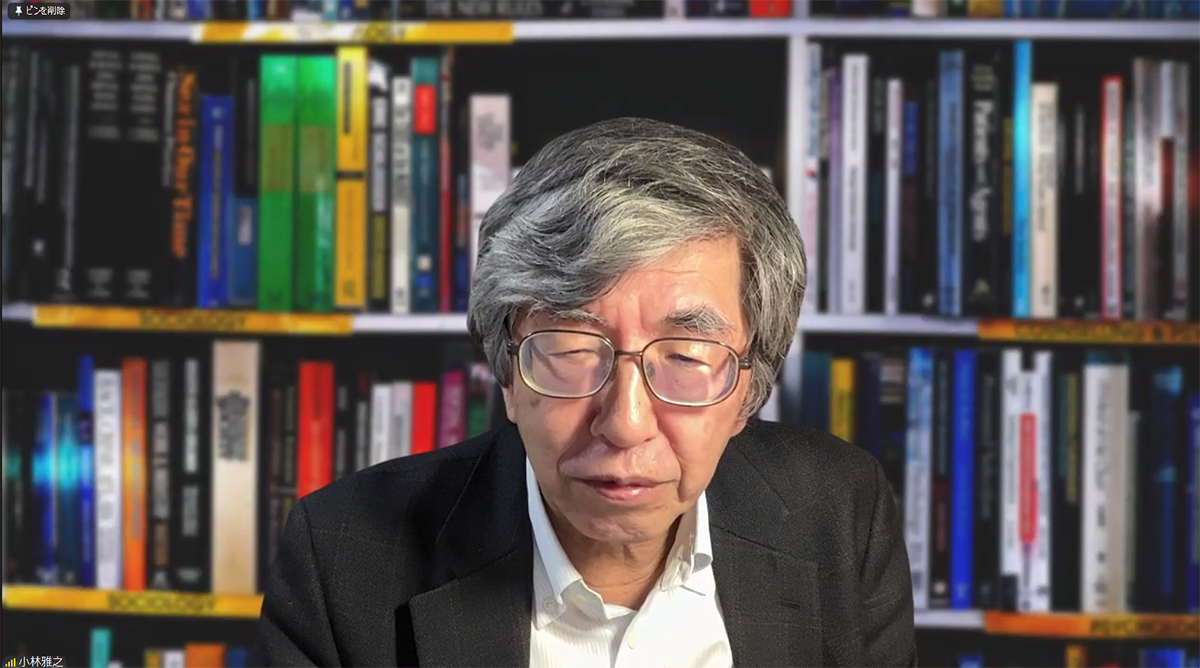家族の「困った」を、社会が「支える」へ
高等教育費負担軽減オンラインセミナー
2025年10月から2026年3月まで毎月1回程度、
全6回すべて無料で受講いただけます。
オンライン形式なので全国どこからでもどなたでも!
高校生や大学生の方のご参加も大歓迎です!
south_east お申し込みはこちら south_west
セミナーの詳細は以下をご覧ください
日本は、高等教育への公的支出がOECD諸国と比べて低い一方で、「高等教育費は家庭が負担すべき」という考え方が根強く残っています。このセミナーでは、「家族の『困った』を、社会が『支える』へ」をテーマに、高等教育費の負担を「個人の自己責任」ではなく「社会全体で支える」という意識改革を目指します。知識の習得だけでなく、参加者の皆様が学びを活かし、新たな連携やつながりを生み出すことを期待しています。
家族の「困った」を、社会が「支える」へ
高等教育費負担軽減オンラインセミナー
- 開講期間
- 2025年10月~2026年3月
- 第1回 2025年10月28日(火) 19:00〜19:40
- 第2回 2025年11月25日(火) 19:00〜19:40
- 第3回 2025年12月18日(木) 19:00〜19:40
- 第4回 2026年 1月20日(火) 19:00〜19:40
- 第5回 2026年 2月17日(火) 19:00〜19:40
- 第6回 2026年 3月12日(木) 19:00〜19:40
- 各回の内容は本ページ下部をご覧ください
- 講座回数
- 全6回
- 講座時間
- 1回40~50分程度を予定
- 内容
- 各回イントロダクション5分+講演35分
- 開催方式
- オンライン開催(Zoomウェビナー)
- 受講料
- 無料(※受講申込必須)
- 受講資格
- 全国どこからでも、どなたでも受講いただけます。
高校生や大学生の皆様、一般の皆様も大歓迎! - 主催
- すべての人が学べる社会へ 高等教育費負担軽減プロジェクト
途中の回からの参加も歓迎します。すでに開催が終了した回についても、受講申込をいただければ見逃し配信(後述の諸注意事項をご覧ください)でご視聴いただくことが可能です。
受講申込方法(本講座は事前のお申し込みが必須です)
- 上の「受講申込」ボタンをクリックして、フォームを開いてください。
- 必要事項を入力して、送信してください。
- フォーム冒頭で入力頂いたメールアドレスに確認メールが届きますので内容をご確認ください。届かない場合は迷惑メールフォルダに分類されていることがありますのでご確認ください。なおも届いていない場合はお問い合わせフォームよりご連絡ください。
- 以上で受講申込は完了です。次の案内をお待ちください。
各回の受講手続き
- 各回の開催前月をめどに、受講申込時にいただいたメールアドレスへ、Zoomウェビナーの招待メールをお送りします。必要事項を入力して送信してください。招待メールは受講申込いただいている方限定でお送りします。招待メールの無断公開・転送・転載は固くお断りいたします。
- すぐにZoomウェビナーより登録確認メールが自動配信されますのでご確認ください。
- 開催日が近づくとZoomウェビナーよりリマインドメールが自動配信されますのでご確認ください。
- 当日開催時間になりましたら②又は③で自動配信されたメールに記載の「ウェビナーに参加」ボタンを押してください。自動的にウェビナーに入室が完了します。
諸注意事項
- 団体、職場等での一括申し込みはできません。お申し込みは必ず個人単位でおこなってください。
- セミナーの模様を録画し、次の開催までの間に「見逃し配信」として受講申込いただいている方々全員へ視聴用URLをお送りします。見逃し配信はYouTubeの限定公開で行い、受講申込いただいている方限定での公開といたします。視聴用URLの無断公開・転送・転載は固くお断りいたします。
- 本セミナーは途中参加可能です。受講申込した時点ですでに開催が終了している回については前述の「見逃し配信」にてすべてご視聴いただけます。
- Zoomウェビナーでは、受講者の顔や声は表示されませんのでご安心ください。
- 各回のセミナーが終了するとZoomウェビナーより受講後アンケートが表示されます。次回の開催に活かしますのでぜひ回答へのご協力をお願いいたします。
- ご不明な点は下記お問い合わせフォームからご連絡ください。
お問い合わせ先
ご不明な点などございましたら下記フォームにてお問い合わせください
プログラム各回のご紹介

国際比較に見る日本の親負担主義の重さ
日本では、他の先進国に比べて高等教育への公財政支出が少なく、その結果私費負担が非常に高くなっています。高校無償化は進みましたが、大学や専門学校へ進学すると高額の学費を家庭で負担しなければなりません。今や高校卒業後に大学や専門学校への進学率は83%超と非常に高くなっています。かたや高等教育に進む半数以上が、日本学生支援機構の奨学金や民間の教育ローンなどを利用しています。せっかく大学に進んでも「4年間学費を払い続けられるのか?」という不安が付き纏いアルバイトに追われる学生も多く、学びを享受できません。貧困の連鎖を断ち切るために、高等教育の学費はどうあるべきか、皆さんと一緒に考えたいと思います。

現在の全国の学生の学費値上げ反対の取組
東大学生として、学費値上げ反対緊急アクションなどで活動。2025年2月より、全国の学生・院生との連携を強化し継続的なロビイングや書籍等の出版活動により輿論を喚起する。これまで3度の院内集会、署名、ZINE出版クラファン、選挙時のアンケート調査等を実施。博士課程の生活費支給の留学生排除問題や、就学支援新制度の成績要件問題など個別イシューの問題提起も行う。東大が値上げを検討した際、波及効果を恐れて学生たちは声を上げた。予想通り、国立大を含め、学費値上げの波が止まらない。名工大や埼大なども値上げ検討。学費・奨学金問題は全世代的な問題であり、経済的格差を教育格差に固定してしまう。物価も家賃も高騰する中、首都圏の大学進学の選択肢を取れる人や家庭はますます限られていく。また個別的なケースに対応できずに困窮する学生が一定数生じている。学費は値下げし無償化が望ましい。

大学を「会社」から「社会」に戻す
日本の大学は、三つの病理を抱えている。第一に、18歳主義。18歳ばかりが入学してくるのは日本だけ。第二は、卒業主義。入学すれば卒業するのは当たり前。91%の修了率だが、圧倒的な世界一。そして、第三が教育費の親負担主義。大学の授業料を親が負担するのはあたり前だと思い込んでいる。この三つのお蔭で高学歴化を達成できたが、今ではそれがブレーキになっている。この三つの病理を規定しているのは、年齢主義的秩序を維持してきた日本の会社である。親負担主義も、50代に所得のピークを迎える年功賃金制度のお蔭である。ところが、この日本的雇用が揺らぎはじめている。大学を「会社」から「社会」に戻す好機が来ている。
終了した回
受講申込いただければすべて見逃し配信で視聴できます。

国際比較に見る日本の親負担主義の重さ
高等教育の費用負担について、3つの教育観と教育費負担観のモデルを提示し国際比較の観点から、日本の教育費負担の現状と問題点を検討し、将来の展望を示す。こうした国際比較によって明らかにされるのは、日本では、教育は家族の責任であるという教育観であり、そのため教育費の親負担がきわめて重いことである。しかし、こうした重い親負担に依存した教育費の負担は限界に来ており、近年、給付型奨学金や新所得連動型奨学金返還制度など、公的負担による家計の教育費負担の軽減策が相次いで導入された。
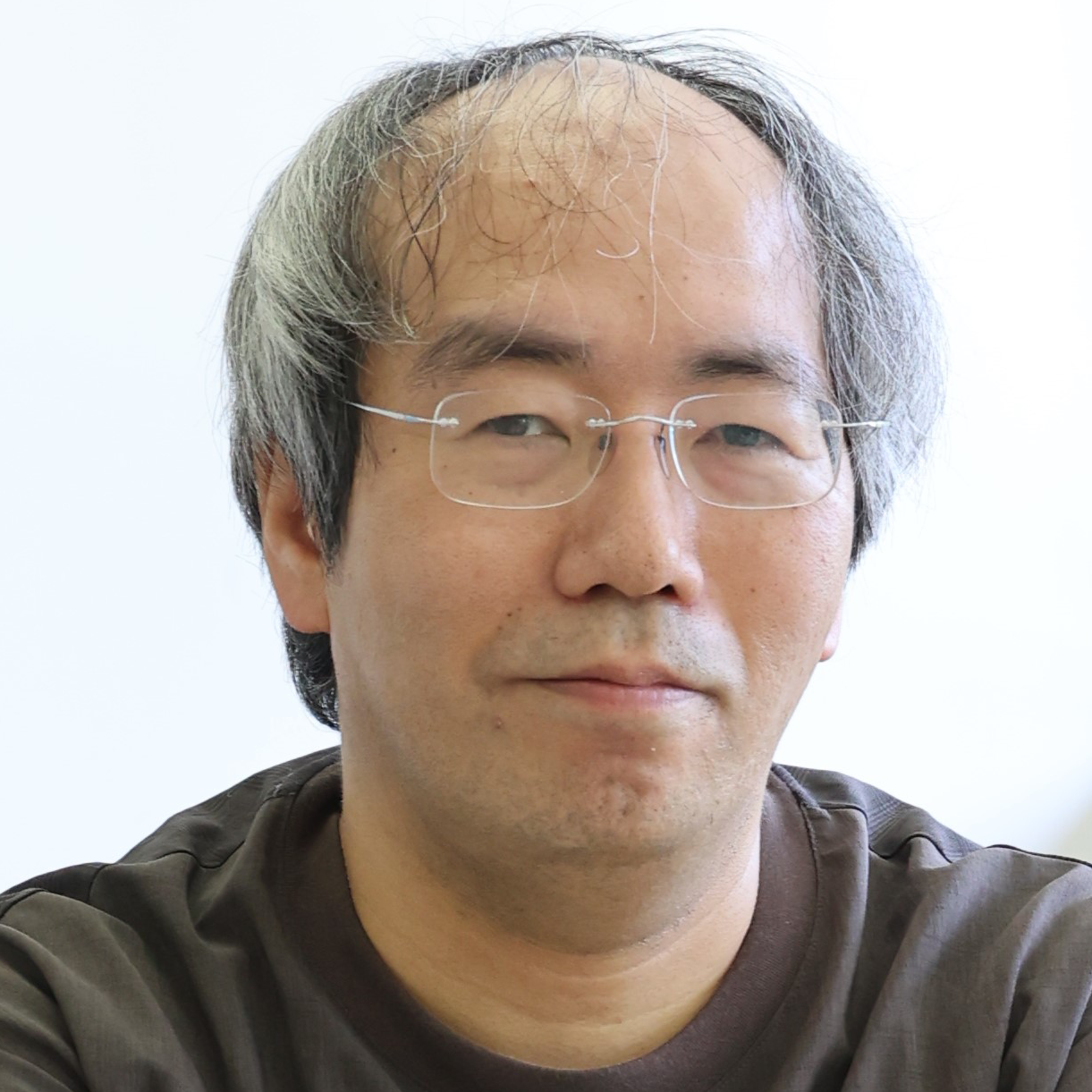
高等教育費における親負担・家族負担主義を考える
戦後日本の高等教育はこれまで、その費用を親や家族が負担する親負担・家族負担を特徴としてきました。政府による高等教育予算支出が少ないなかでも、高等教育への進学率が上昇してきたのは、高等教育費を親や家族が負担するのは当然とする意識が強かったからに他なりません。しかし、現在高等教育費における親負担・家族負担主義が限界に達しています。高等教育費における親負担・家族負担主義の現状を分析し、今後の望ましいあり方について考察します。
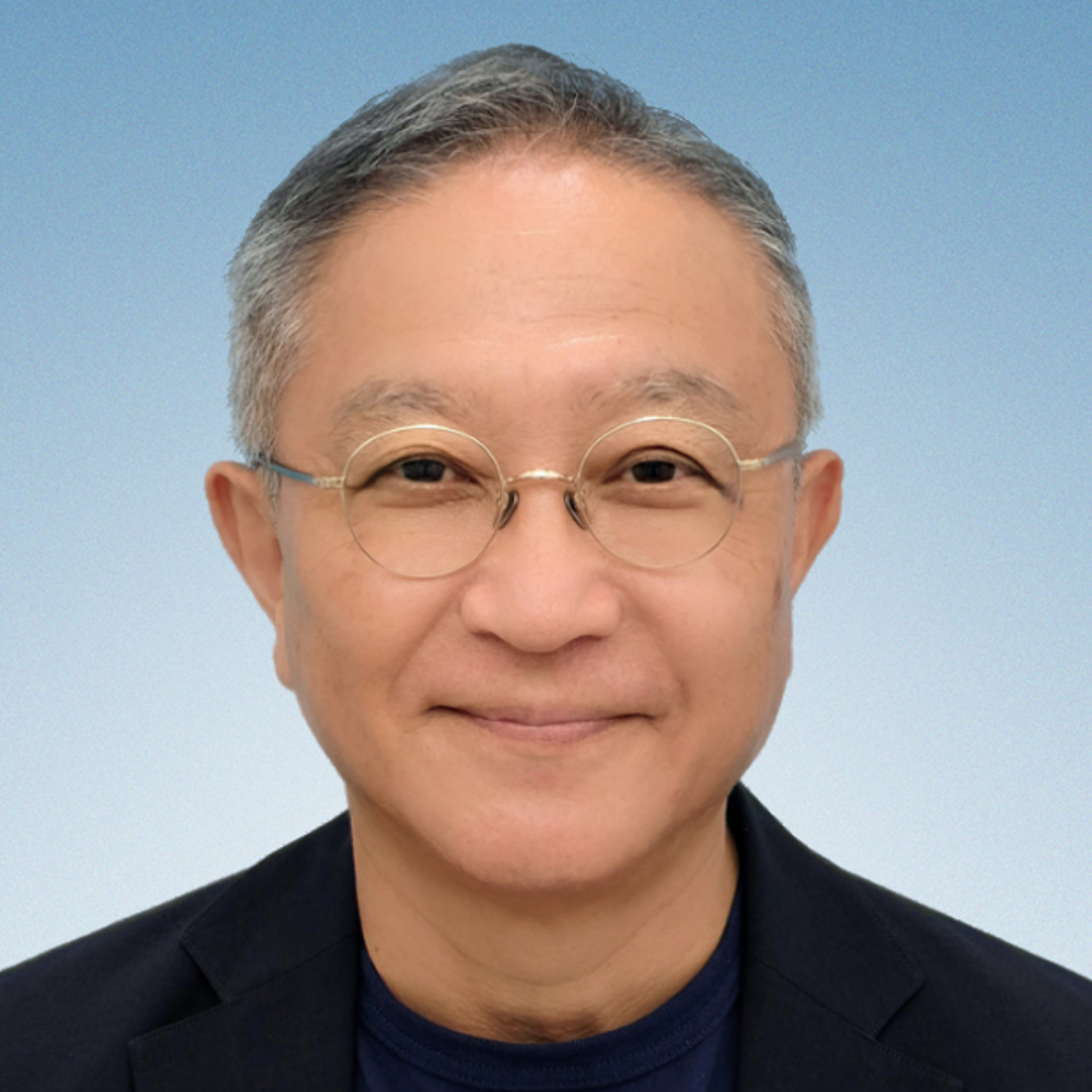
借主と家族を苦しめる貸与奨学金の負担
将来の仕事や収入が分からない時に借りる貸与奨学金は、利用の最初から返済困難に陥るリスクを抱えています。日本学生支援機構の貸与奨学金における返還期限の猶予、減額返還、返還免除などの返済困難者に対する救済制度は、利用条件や運用により救済に限度があります。親や親族などの保証人の負担も大きく、保証人への影響をおそれて、自己破産などの法的債務整理を嫌い、無理な返済を続ける人が少なくありません。
本講では、生まれ育った環境に関わらず、個人の自由な選択を保障するための奨学金が、実際には個人の生き方を制限し、家族に縛り付けている現状とその構造的要因について考えます。